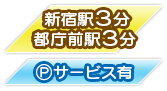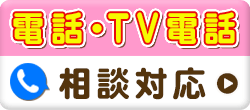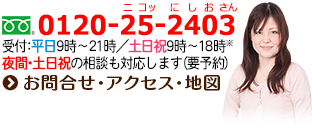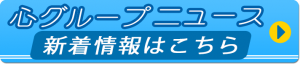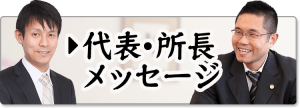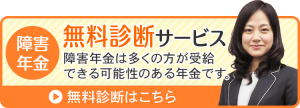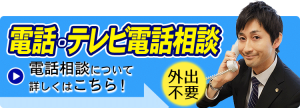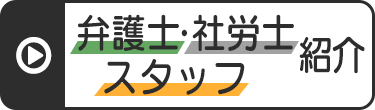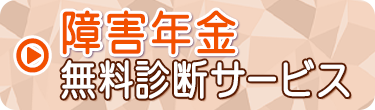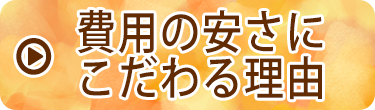肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
1 肺結核の障害認定基準
肺結核で障害年金を請求する場合、「呼吸器疾患による障害」として、等級の認定がなされます。
呼吸器疾患による障害の認定基準は以下のとおりです。
【第1級】
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、身の回りのことを一人ですませるのを不可能とさせる程度のものが該当します。
【第2級】
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが該当します。
【第3級】
身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものが該当します。
2 肺結核の認定要領
認定基準の中に定められている認定要領では、より具体的に等級を認定する基準が定められています。
それによると、肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。
⑴ 病状判定
肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等によって総合的に認定されます。
⑵ 機能判定
肺結核の機能判定は、呼吸不全の認定要領に従って行われます。
呼吸不全の認定要領には、各等級に該当するものとして以下が例示されています。
【1級】
動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
【2級】
動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
【3級】
動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
3 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
このように、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の検査成績のみならず、日常生活や仕事への制限の程度が重視されますので、日ごろから、日常生活で発生している支障の内容や程度、他人の支援の有無や内容、仕事への影響の有無や程度などについて、しっかりと話をしておき、診断書に反映してもらうことが重要です。