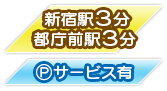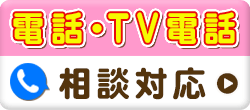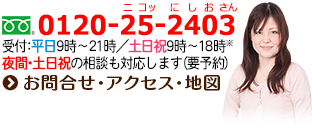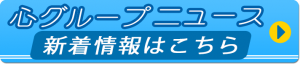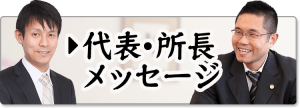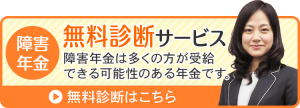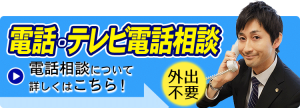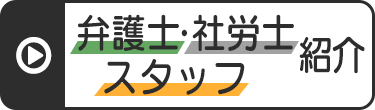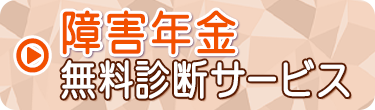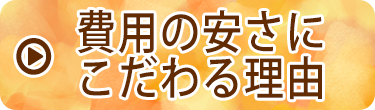障害年金における初診日
1 初診日とは
初診日については、日本年金機構のホームページで公表されている障害年金認定基準で定義を確認することができます。
同基準では、初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」と定義されています。
2 医師又は歯科医師の診療という点について
ここで重要なことが、「医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされていることです。
そのため、例えば、心身の不調を訴えて、医師のいない学校の保険室等で処置を受けただけの場合や、大学や会社などで設置されているメンタルヘルス関係のカウンセリングを受けただけの場合には、初診日とは認められません。
初診日と認められるには、医師又は歯科医師に診察をしてもらうことが必要です。
3 健康診断の扱いについていて
医師や歯科医師が所属している医療機関に行っていた場合でも、健康診断は原則として初診日としては扱われません。
健康診断はあくまで一般的な健康状態のチェックのためのものであり、障害の原因となった傷病について診察を受けたとは認められないのが原則です。
したがって、A病院で会社の健康診断を受けて異常を指摘され、自宅近くのB病院を受診した場合には、B病院を初めて受診した日が初診日となります、
ただし、B病院がすでに閉院している、またはB病院にカルテが残っていないため初診日の証明が困難な場合、A病院に健康診断の結果が残っており、治療が必要なほどの状態であった場合には、例外的に、健康診断を受けた日が初診日と認められる場合があります。
4 病名が変わっている場合
同じ症状で受診していても、なかなか診断名が付かなかったり、診断名が変わったりする場合も多いです。
このような場合、障害年金の初診日の定義は上記1のとおり、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」であることから、受診していた症状が一連のものであれば、その症状で一番初めに受診した日が初診日となります。
また、例えば糖尿病の合併症として眼、腎臓、神経等の合併症を発症した場合には、糖尿病で初めて受診した日が初診日となります。
ただし、ある病気を原因として別の病気や障害が発生している場合でも、両者に経験則上通常であるといえるような明らかな因果関係がない場合には、後から生じた病気や障害で初めて受診した日が初診日となります。
具体的には、高血圧で治療を受けた人が脳出血を発症しても、原則として高血圧で初めて受診した日が初診日とはならず、脳出血で初めて受診した日が初診日となります。