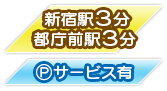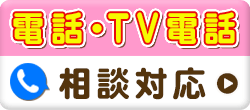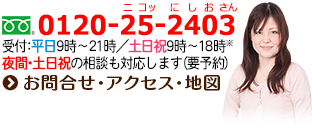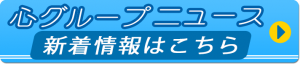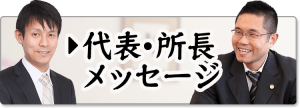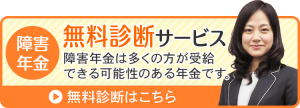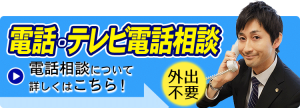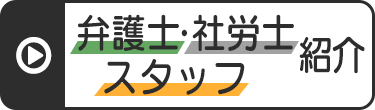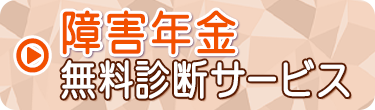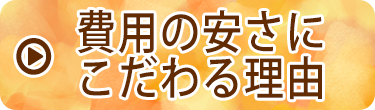学習障害で障害年金が受け取れる場合
1 学習障害の障害年金認定基準の分類
学習障害も障害年金の受給対象となっています。
障害年金認定基準上、学習障害は広く発達障害の一種として分類され、自閉症、アスペルガー症候群等と同一の基準で障害年金を受け取ることができるかどうかが判断されています。
2 初診日の特定
障害年金申請全般で重要となりますが、障害年金の申請にあたっては、原則として初診日(申請傷病に関して初めて医療機関を受診した日)が特定されていることが求められます。
もっとも、幼少期に通院をはじめた方の場合には、通常20歳前障害基礎年金となるため、20歳前のどこかで通院していることが証明できれば足りるケースもあります。
大人になってから学習障害と診断された場合には、原則どおり、初めて医療機関を受診した日(心療内科等になる場合が多いと思います。)が初診日となります。
3 保険料の納付
初診日が20歳以前の場合(20歳前障害基礎年金の申請となる場合)、初診日時点で保険料納付の義務が生じていないことから保険料納付はそもそも問題となりませんが、初診日が20歳を超えている場合、保険料の納付状況が要件となってきます。
保険料が一定期間以上未納となっていると、現在の症状がいかに重くても、障害年金の受給は認められません。
具体的要件は、①初診日の属する月の前々月時点まで直近1年間未納がない、②初診日の前々月まで全年金制度加入期間の1/3を超える未納がないかのどちらかを満たしている、となっています。
免除手続きを行った上での未払いは未納とされません。
ただし、初診日の前日を基準時として要件を満たしているか判断するので、障害年金の申請をしようと思って未納分について後日免除手続きをとっても、初診日の前日時点で未納であれば遡って要件を充足したものとは扱われません。
4 基準を満たす障害状態にあること
上記2つの要件を満たしていると、あとは日本年金機構の審査によって受給の可否が決められることになります。
学習障害についての審査は、個々人の症状が千差万別であるため、総合的な観点から判断されます。
審査基準をみても、「知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされているように、検査数値等で判断されないというのが、学習障害の障害年金申請の難しい点だといえます。
障害年金の大きな枠組みとして、労働に著しい制限があれば3級程度、日常生活に著しい制限がある場合には2級程度とされていますが、軽度の学習障害のみ発現している方の場合、仕事自体はできており、収入も得られているような方も少なからずいます。
そういった方の場合、学習障害のみでは障害状態の判断により、障害年金を受け取れない場合もあります。
こういったケースでは、審査基準において「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する」とされているとおり、実態としての就労状況(雇用形態や業務内容、周囲の援助の程度等)がしっかり分かるように申請することも求められます。